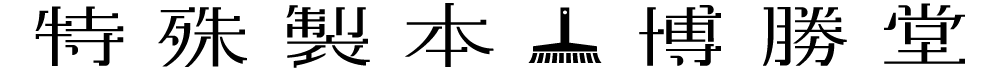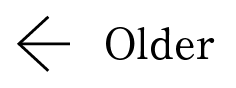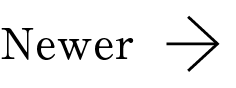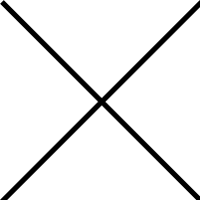News
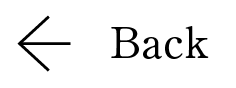
久々の小道具シリーズ
2017年10月25日
秋、、、を通り越して急に冬になってしまいましたね。゚(゚´ω`゚)゚。
さむい日が続いていますが、みなさん風邪などひいていませんか
さてさて、最近の博勝堂はといいますと、相変わらずいろんなことをやっております。
国内外問わず、10月11月はアートブックフェアが多いようで、写真集の製本が多かった印象でした。
年末に向けて、御朱印帳も爆発しており、
お経本や巻秩もあったり、三つ目綴じも2〜3点、、、いろーんな仕事が流れている博勝堂の現場なのでした
お仕事を頂けることに感謝しつつ、お客様の期待にいつでもお応えできるよう、日々精進致します
さー今日のブログは久々の小道具ネタにしようと思います
ご存じない方は古い記事を遡ってみてみてくださいね
なななんと!
20年ぶり(会長談)に引っ張り出してみました!
膠を溶かす湯煎のお鍋〜〜
水を入れてみたらそこここからピューっと、
漏れる漏れる!笑
会長に手伝ってもらい、
アルミ箔をたくさん切り貼りして、修理からのスタートでした
私は造本設計課で束見本を日々作製しているのですが、最近はこれぐらいの本の開きにしてほしい!や、かたーいくてあつーい紙で作りたいが、壊れないか?など、開き具合というのを重要視されるお客様が多いのです。
束見本の数では、本番の機械は通せません。゚(゚´ω`゚)゚。
基本的に手で作製します。
ただ、実際に弊社の現場から生み出される本に準じたものをお客様に渡せないと意味がありません。。。
綺麗に作りすぎても、本番はそうはいかないこともありますし、束見本で実現できても、本番の量産が難しくなってしまうこともあります。
そんな中、最近頭を悩ませていたのが、背加工でした
本番は膠で背加工をしますが、束見本では、膠の強度を背固め用のボンドと厚手の地券紙で再現していました。
ただ、どーしても膠のしなやかさがボンドでは再現できません。。。
うーむ、こうなったら本番同様の膠を使うしかない!
ということで、会長に相談し、古ーいお鍋を引っ張り出して頂きました
このお鍋は二重構造になっていて、湯煎されるようになっています
60℃ほどで溶けてくれますー^^
ビジュアルは毒々しいですね、!笑

このように、刷毛で膠を盛ってゆきます。
塗り重ねながら、寒冷紗、皺紙、地券紙を付けます。
数時間置いて、膠の余分な水分が飛んだら完成です╰(*´︶`*)╯
ボンドにはないしなやかな開きが表現できました
ちなみに、銀色の金具が付いたこの刷毛、、、
かっこよくないですか
膠用の刷毛なるものらしいです。。。
カッコいいです。。笑
お鍋が熱くなっても、刷毛が傷まないようになっています
他の製本用の刷毛と比べて、毛足が長く、毛のボリュームもあり、ふかふかしている印象です。
カタカナの”ニカワ”の文字もなんだか歴史を感じますね(๑˃̵ᴗ˂̵)
そんなこんなで、みなさんもたまーにお手元の本の開き具合、チェックしてみてくださいね
奥深い背固めのお話でした(*´◒`*)